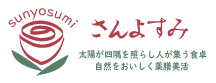研修旅行記:笑顔のあまりない街の視線と熱い盛り盛り料理
春のイスタンブールの食旅(ケバブと鯖サンドの香りー)に続き、次の旅先は薬膳学を学んだ学院の研修旅行で北京へ。初めての中国渡航、しかも時期が、「抗日戦争勝利80周年」の直後で、反日映画がアメリカで先行上映されている最中でした。旅行申し込み時には知らなかった情報だったため、石を投げられはしないまでも、冷たい視線を浴びるのではと折角の旅なのに出発前は少し憂鬱でした。
さらに、アリペイの登録や百度地図の利用など、中国語が全くできない自分にとっては不安要素だらけ。しかし、だからこそ団体での研修旅行は貴重な機会でした。
時間の都合上、書きたいことの一部になりますが、印象深い料理や街の雑感など、超偏向的に報告をします。
北京の初印象:厳戒態勢と大国の日常
北京に降り立ってまず驚いたのは、そのクリーンな見た目です。6〜8車線ほどの広い道路にはEV車や高級外車が走り、戦争勝利記念パレードの後ということもあったのか、ゴミ一つ見られずとても綺麗でした。
街のあちこちには警察(公安や自衛隊など)や監視カメラがあり、厳戒態勢が敷かれている印象です。有名観光地では、中国語と英語表記しか目にしませんでした(日本との違いを想像してください)。今まで訪ねたどの都市も親日的な場所ばかりだったので、向こうから日本語で挨拶されたり、呼び込みをされることは皆無。突然中国語で話しかけられることはあっても、研修先の大学や指定の店以外では、歓迎されている雰囲気は感じられませんでした。
笑顔での接客もあまりありませんが、その代わり押し売りもなく、うるさくないのは気楽でした。
お土産通りや下町に行くと雰囲気はガラッと変わります。まだ暑かったせいか、上半身裸のおじさん、またはTシャツをお腹だけ捲り上げた人や、柄シャツを前全開で着ている人が多く、それがなんとも印象的でした。
記憶に刻まれた宮廷料理と薬膳料理
華麗なる宮廷料理
記憶に残る料理の一つ目は、聖徳楼飯荘(中国語では異なる漢字)で食べた宮廷料理です。見た目も味も素晴らしかったです。高級店らしく、入口から部屋までがとても長い堂々とした廊下で、オーナーはとてもにこやかで綺麗なマダムでした。中華料理は揚げ物が多く、日本人の胃に重たいのですが、そうでないあっさりした味付けもあり、特に海老料理が美味しかったです。


下の写真は、おこげのあんかけで、中身は空洞です。おこげは、気力の足りない時や消化不良や下痢にアプローチします。デザートの前、かなり後半になってから出てきました。あんかけおこげ料理は店で食べたことがありますが、このドーム型は、迫力があり、感動します。
保存ご飯を焼き付けて、野菜を入れてあんかけにするのなら家でも応用できますね。餅でもいいですね。作ってみましょうかね。

食器は、蓮の葉っぱのイメージ。

枸杞子 とともに最も活躍している棗の実です。香りも水分も薄い若い林檎の味。

定番料理の悩み
どこの店でも出てきた北京ダックは、正直なところ味の違いがわかりませんでした。クレープに鶏肉と野菜を挟み、味噌を付けて食べますが、円卓で回すため、好きな具材をたくさん取れないのが少し気を使うメニューでした。ちなみに、お土産の真空パックの北京ダックは美味しくないので買ってはいけないそうです。
理化学研究所と共同開発された薬膳料理の店
記憶に残る料理の二つ目、最も食の進んだ料理で、素晴らしく美味しかった本格的薬膳料理の店です。すぐに無くなってしまい、デザートを少し食べ損ないました。とてもやさしい味付けの料理で癒されました。豆腐をはじめ野菜が多かったですね。湯葉に似た豆腐皮を野菜で巻いたあっさりしたおかずと見た目がココアパンなのに、霊芝と少しオニオンの入ったパンは塩味も砂糖の味も感じられないのですが、美味しくてすぐ無くなりました。


下写真は、手打ち麺入り



中衛御苑福膳というお店です。北京中心街から車で1時間弱でした。
秋は潤肺 研修先の薬膳
薬膳で潤肺(肺を潤す)作用がある代表的な食材は梨です。特に秋の乾燥による空咳、のどの渇きの緩和に役立ちます。 研修先では、秋の養生のシロップとして秋梨膏(しゅうりこう)を作りました。梨5個分ぐらいで中サイズのジャム瓶に軽く収まる程度で、ピュアなら非常に貴重なものです。秋梨膏は、観光客用のお菓子売り場にもシロップが小さいパックにして売ってあります。どこまでピュアかは知りませんが。他にも棗あんの山薬のだんごなど健康的なお菓子を作りました。
それから初めて研修で飲んだ酸梅湯(さんめいたん)は、家でも作ってみました。
これは、特に暑い夏に疲れて汗をかいて喉が渇いた時に飲めば、疲労回復になるし、味も癖になりそうな美味しさです。
酸梅湯の材料
・鳥梅(うばい・うーめい)—20g 若い梅をスモークしたものです 梅干しや梅酒の梅使用はだめです
・山査子(さんざし)—8g お菓子になったサンザシではありません
・甘草(かんぞう)—葉っぱ大のもの3片 味の調整役としても良く使われます
・黒糖 お好みで
・水—1リットル 煮詰めるから水分は半分になります

鳥梅 山査子 甘草を1時間漬ける。その後水1リットル入れて30分煮詰めます。何回かに分けて味見しながら黒糖も加えます。
最終的に水分量は半分になります。スモーキーな梅ジュースです。
こちらに酸梅湯の作り方動画 Instagram
記憶に残る料理の三つ目、研修先の大学の学食には、ビュッフェ形式の薬膳コーナーがあり、おかずの内容が学問的に解説されていました。日常に薬膳が根付いていることに感銘を受けました。今回の旅で食事した店もここの学食も海老が沢山使われている印象でしたね。
中医学の偉人達
大学の学食は、ビュッフェ式のコーナーが薬膳になっていました。おかずの内容が学問的に解説されていました。
中医学の偉人達。大学の食堂の壁に貼ってあったもので内容全てAI和訳
 扁鵲(へんじゃく)
扁鵲(へんじゃく)
紀元前407年 – 紀元前310年ごろ。嬴姓(えいせい)、秦氏(しんし)。
春秋戦国時代の渤海郡鄭(現在の河北省滄州市任丘市)の出身。
若い頃に長桑君(ちょうそうくん) に師事して医学を学び、その医术と禁方(秘伝の処方) のすべてを伝授された。その後、
· 趙では婦人科として、· 斉では五官科として、· 周では小児科として、名声を天下に轟かせた。
しかし、その医学の技術が彼に及ばない者に妬まれ、
扁鵲は中医学の脈診による診断方法の基礎を確立し、
 張仲景(ちょう ちゅうけい) (西暦150年頃 – 219年頃)
張仲景(ちょう ちゅうけい) (西暦150年頃 – 219年頃)
字は仲景。後漢時代の南陽郡涅陽県(
張仲景は広く医方(処方)を収集・研究し、
方剤学(漢方処方学)の方面においても、『傷寒雑病論』
主要な業績:
· 『傷寒雑病論』の著者。これは後に『傷寒論』と『金匱要略』
· 弁証論治体系の確立。中医学の臨床における基本原則です。
· 六経弁証や八綱弁証など、具体的な診断体系の構築。
· 数多くの有効な漢方処方(方剤)を後世に残しました。
 皇甫謐(こうほ ひつ) (215年—282年)
皇甫謐(こうほ ひつ) (215年—282年)
幼名は静、字は士安、自らを玄晏先生(げんあんせんせい)
彼は一生を著述業に捧げた。後に風痺疾(
その著作『针灸甲乙经』(しんきゅうこうおつきょう)は、
此外,他还编撰了《历代帝王世纪》、《高士传》、《逸士传》、《
主要な業績:
· 『针灸甲乙经』: 针灸理論と臨床を体系化した最初の専門書。
· 歴史書や伝記の編纂。
 葛洪(かっ こう) (西暦281年~341年※)
葛洪(かっ こう) (西暦281年~341年※)
字は雅川、自らを抱朴子(ほうぼくし)と号した。
葛洪は中国東晋時代を代表する医師であり、
著書『肘後方』(ちゅうごほう)の中で、天花(天然痘)
また、煉丹の方面においても非常に造詣が深く、著書『抱朴子・
主要な業績:
· 『肘後備急方』: 緊急医療の手引書。伝染病の記載で有名。
· 『抱朴子』: 神仙思想や煉丹術について記した書物。内篇(道教・仙術)
· 予防医学や化学の先駆者としての業績が特に重要視されています。
 華佗
華佗
華佗(かだ)(生没年:約 145年 – 208年)。字は元化、一名を旉(ふ)といい、沛国譙県(
華佗は董奉(とうほう)、張仲景(ちょうちゅうけい)と並んで「
その医术は広範にわたり、特に外科を得意とし、
晚年、曹操(そうそう)の疑いを買い、
華佗は後世の人々から「外科の聖手」、「外科の鼻祖」
 孫 思邈(そん しばく)(581年 – 682年)
孫 思邈(そん しばく)(581年 – 682年)
京兆華原(現在の陕西省銅川市耀州区)の出身。
西暦581年、貧しい農家に生まれる。幼少の頃から聡明で、
当時は社会が動乱していたため、
時の朝廷は彼を国子監の博士に任命しようとしたが、
孫思邈は太白山で道家の経典を研究する傍ら、
主要な業績:
· 医学書『千金要方』『千金翼方』を著し、
· 「大医精誠」という医の倫理を説いた文章を残し、
 朱丹溪(しゅ たんけい)
朱丹溪(しゅ たんけい)
朱 震亨(しゅ しんこう)、朱丹溪(しゅ たんけい) として広く知られる(1281年 – 1358年)。名は震亨、字は彦修。元代の著名な医学者。
かつて住んだ邸宅の傍らに「丹溪」
朱丹溪の医术は極めて高く、
「陽常に有余、陰常に不足す」(
劉完素、張従正、李杲(李東垣)と並んで「金元四大家」
 李 時珍(り じちん) (1518年 – 1593年)
李 時珍(り じちん) (1518年 – 1593年)
武当山、廬山、茅山、牛首山など、および湖北、安徽、河南、
 葉天士
葉天士

もし、間違っている内容がありましたらSNSメッセージでご指摘ください。
北京旅行おまけ話
海外旅に出ると日本の良さを痛いほど感じますが、中国はそれを最も痛感させてくれる国でした。天安門広場に入るまでの検閲が細かいです。メモ帳型携帯カバーの方は、台湾人や韓国人の名刺など入れておかないようにしましょう。
人民解放軍の行進を見ることが出来たので、撮影して、Lineの家族グループに送りました。すると日も浅いうちからその写真や動画と公安警察の車をバスから撮った写真が黒く期限切れて見れなくなっていました。他の写真は前後ともに見れているのにです。Lineは国内に工作員がいるのでしょうか?ああ、監視されているなと思いました。
皆さん、大事な数字やパスワードは、メールにするなり、慎重に取り扱いしましょう。そして中華アプリのなかには、天安門ワードと台湾の旗マークが絶対排除のものもあります。
天安門広場の下の写真の右上は監視カメラです。それ以外にもどんだけ~ってくらいカメラが付いています。

以下食事中注意!
トイレ事情は、インドの方がうんとマシです。ちゃんと手動シャワーがありますし、基本座る洋式です。ベトナムもトルコ、イスタンブールもマレーシアのクアラルンプールもそうです。
空港以外の有名な観光施設やレストランは、10個室につき1~2個だけ洋式の割合が多いです。場所は、明かしませんが、トイレのドアが丸ごと外れた事件もありました。そして、この事件のあとにもっと驚くことがありました。レストランにトイレが無いので案内された所に行くと、そこは、あのニーハオトイレでした。まさか大都会で、そんな経験をするとは思っていませんでした。ニーハオトイレとは、仕切りが無く、ニーハオと挨拶しながら用を足せるトイレです。しかも紙の備え付けがありませんでした。持ち前で使った紙を外の道路にあるごみ箱に捨てます!
手を洗う所は?店に戻ったら、手招きされて、店の人が野菜も洗っている水道口で手を洗いました。すっかり食べる気を無くしてしまいました。そこは大きな焼き肉店でした。近所の民家は、まだお風呂もトイレも無い家もあり、おまるを溜めてからニーハオトイレに流しにくる人もいるようです。都会、北京市ですけどね。
↓ 折角なので、リアルに実際使ったトイレです。奥が洋式。扉の前で見張りしてもらいました。2025年です。

お目汚ししてしまったので、最後に美しい写真を。
以下は、炸醤麺を食べた大海碗さんのお店で撮った写真、エプロンをこんな風にして垂らすのも便利でスマートですね。

それから、ベトナムをはじめとしたアジア国食の旅レポを時間許すならまた投稿していきます。