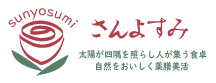ここ2年の間に、いずれも短期間ではありますが、ベトナムのハノイとホーチミン、マレーシアのクアラルンプール、トルコのイスタンブール、中国の北京を旅しました。円安の影響で、まだ大好きなヨーロッパには行く余裕がありませんが、どれも初めて訪れる国でした。
これまで年に数回も海外へ行くことはありませんでしたが、年齢的なこともあって「もういつ介護などで行けなくなるかわからない」と感じています。人生は短い。だからこそ、予算の許す限り「行きたいときが旅どき」です。
その国の食は体型見れば結果が出ている
ブログには書いていませんが、コロナ禍が明けた2023年に、初めてインドを訪れました。インドは糖尿病が国民病ともいわれるほど多く、お菓子には大量の砂糖が使われ、油の使用量も非常に多い国です。
揚げ菓子に砂糖をたっぷりまぶすような食文化が定着しており、肥満の要因が多いのも納得できます。宗教上の理由でベジタリアンが多いことも、却って甘いお菓子を求める傾向を強めているように感じました。街を歩いていても、男女ともにふくよかな人を多く見かけました。
スパイスの国らしく、インドのカレーはまさに薬膳そのものです。食卓にはハエが飛び、手で払いのけながら食べたこともあります。調理した料理をケースにも冷蔵庫にも入れずに並べている店もありましたが、それでも現地の人々が食中毒を起こさないのは、ターメリックをはじめとするスパイスの強い殺菌作用のおかげかもしれません。
太った人を見なかったベトナム
そのインドとまったく対照的だったのがベトナムです。街を歩いても、太った人をほとんど見かけません。お腹の出ている人すら珍しかったです。
主食は米粉の麺で、豚肉も炭火で焼いたものが中心。小麦ではなく米が主流なのは、単に「小麦が入ってこなかったから」ではなく、稲作が圧倒的に盛んで、豊富に米がとれたためだそうです。
小麦粉がベトナムに本格的に入ってきたのは、19世紀後半のフランス植民地時代。フランスから小麦粉や乳製品、バゲット文化が伝わり、それをベトナム人が工夫して誕生したのが、現在のバインミーです。小麦粉に少し米粉を混ぜるようになったのも、第一次世界大戦で小麦が不足したのがきっかけでした。異文化が混ざり合い、ベトナムらしいパン食が生まれたのです。
ビーガン食のレストランもよく目にしました。南国ならではの野菜やフルーツを色鮮やかに組み合わせた芸術のような一皿もあり、嬉しい驚きでした。デザインが洗練されている店が多く本当に勉強になります。

日本でもフォーの麺は買うことが出来るので、麺類が食べたいなと思ったら作っています。
真っ先に市場に行く計画を立てます
私は旅に出ると、朝市などの市場をぶらぶら歩くのが大好きです。フルーツを買ってその場で食べるのが楽しみなので、いつも果物ナイフをスーツケースに入れています。訪れるのはほとんど暑い国ばかりで、たとえばインドの市場もフルーツや野菜がとても豊富です。
一方、ベトナムのハノイの市場では「薬膳」の雰囲気がより強く感じられます。たとえば、たけのこの干しものを目にしたのもハノイが初めてでしたし、これまで見た中で一番長いシナモン(桂皮)を手に取ったのもハノイの市場でした。漢方街もあるし、そう考えると、一番マニアックな市場はもしかしたらハノイかもしれません。

クアラルンプールでは、デザートに野菜や豆がよく使われていて、中華をアレンジしたマイルドな料理も多く見かけました。大きなチャイナタウンには漢方薬局もあり、健康志向の商品が並んでいるのも興味深かったです。燕の巣を原料にした甘味料もお土産に購入しました。インド、中国、マレーシアが混じり合ったような多国籍感は、シンガポールの食文化にも通じるものがあります。
日本の高級しいたけが漢方薬局で売られていたのが印象的でした。
この街の料理はどれも辛すぎず、南国らしいまろやかさがあってとてもおいしいです。
バクテー(骨肉茶)には羅漢果が使われていて、自然な甘みとやさしい味わいがあり、やさしく体にしみ入るようでした。

⇒日本人シニア移住人気No1のマレーシアの何が良いのか一度行ってみた
トルコのイスタンブールは、アジアとヨーロッパの両方にまたがる街でありながら、意外とコンパクトで歩きやすく、何重にも楽しめる場所でした。
ガラタ橋のたもとで食べたサバサンドは有名どおりの美味しさで、帰国後さっそく自宅でも作ってみたほどです。
日本ではなかなか手に入らないザクロも、現地では新鮮な果汁や乾燥果実が豊富に売られています。乾燥ザクロは、お茶や料理に使えてとても重宝するので、もっと買って帰ればよかったと少し後悔しています。
炭火で香ばしく焼かれたケバブもまた格別で、日本ではなかなか味わえない本場の深みがありました。
ただひとつ気をつけたいのは、トルコの伝統菓子の甘さ。バクラヴァなどは美しい見た目とは裏腹に、日本人には少し甘すぎるかもしれません。けれど、濃いトルココーヒーと合わせていただくと、異国の甘味の魅力が少しわかる気がしました。
再現した料理はトルコでヒントをもらったものが多いです。

鯖と大根菜のトースト
お米プリンやマッシュポテトもトルコから帰国してからすぐ作りました。
⇒ケバブと鯖サンドの香りーイスタンブールの食旅 思い出その1
⇒激甘だけじゃないヘルシーなトルコお菓子と自然派商品 食旅思い出その2
油っこい中華料理と味も効能も見た目も計算しつくされた薬膳料理
記憶に新しい北京での研修でした。団体行動だったので気軽な軽食はできませんでしたが、本にも掲載されていない初めて目にし、口にする薬膳料理が絶品でした。中華料理はどうしたって油っぽいじゃないですか。野菜を豆腐皮で巻いたものや花茶に心身ともに癒されました。
家で再現した酸梅湯は、夏にぴったりの飲み物でした。もう秋になってしまい残念なほどです。
C国は、大変難しく恐ろしい国ではありますが、先人の知恵は、とても貴重でありがたいです。早く昔の良き国に戻って欲しいです。
さて、2026は、台湾からです。
またレポートしますね。