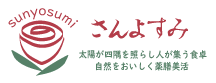突然、頭の先から足の裏まで痒みに襲われた
3月後半になるとスギ花粉が飛散し始めるため、スギ花粉アレルギーのある人は症状が出始め、マスク姿の人も増えます。私は昔からスギ花粉アレルギーとは無縁で、5月以降に飛ぶブタクサ系の酷い花粉症も、ずいぶん前に克服しました。その経緯については、こちらを記事にまとめています。
ところが、3月23日ごろから徐々に鼻水やくしゃみが出始めました。「えっ、もしかしてスギ花粉症を発症した? それとも、せっかく克服したアレルギーが復活した?」と驚きました。そして26日、外出先で鼻水が止まらなくなり、突然、全身の痒みに襲われました。さらに頭がぼんやりし、体がだるくなってきたのです。
そんなとき、ネットニュースで「3月25日、黄砂に注意!」という記事を見つけました。私はマスクをせずに外出し、花粉カットスプレーを顔にかけるのを忘れていたことを激しく後悔しました。私が住む関西は特に黄砂が多く、洗車したばかりの車のボンネットにびっしり砂が付着している記事も沢山見ました。
朝食前に小青竜湯を飲み、症状がひどくなりそうなら抗ヒスタミン剤を少しだけ服用するようにしました。幸い、鼻水や咳の症状は治まりましたが、皮膚の痒みが主な症状として残っています。
体質が変わっている可能性もあるので、アレルギー検査を受けるのもいいかもしれません。調べてみると、黄砂にはPM2.5などの微粒子が付着しており、花粉よりもはるかに小さいとのこと。そんなものを吸い込んでいたのかと思うと、恐ろしくなります。
また、抗ヒスタミン剤を飲み続けると、体が慣れて効きにくくなることもあるため、普段の食事にもアレルギー反応を和らげる食薬を取り入れることが大切です。今回は、身近なものから漢方に使われるものまで、いくつかピックアップしてご紹介します。
痒みを抑える抗炎症作用のある生薬(ハーブ)
紫蘇(シソ)
紫蘇は身体を温める温性食薬です。刺身のつまに使われる緑の葉は青紫蘇、梅干しとともに漬ける赤紫蘇は紫蘇漬けや紫蘇ジュースに使われます。市場に赤紫蘇が出回るのは5月ごろですが、これを煮出してレモン汁を加えると、鮮やかな赤色のジュースになります。
紫蘇には抗アレルギー作用があり、ロズマリン酸やルテオリンがヒスタミンの過剰分泌を抑制し、アレルギー症状の緩和や痒みに効果的です。
私自身、花粉症がひどかったころによく紫蘇ジュースを作っていました。即効性はないかもしれませんが、ゼリーにしたり、抗菌・抗ウイルス作用を活かして日常的に摂るのもおすすめです。青紫蘇(大葉)が刺身に添えられているのも、理にかなっていますね。
紫蘇が配合されている漢方薬は、部位によって異なります。
• 紫蘇の葉 … 風邪の初期症状に用いられる「香蘇散」
• 紫蘇の種子 … 咳や痰の改善に使われる「半夏厚朴湯」
薄荷;ミント
ハッカ飴やミント飴は手軽ですが、糖分が多くなりがち(経験済み)なので、ミントティーの方がおすすめです。また、「クリスタルミント」というメントールの結晶を使うと、鼻の通りがよくなり、リフレッシュできます。
使い方は簡単で、2パターン
1. クリスタルミントをほんの少し口に入れる(写真参照)
2. コップにお湯を張り、わずかなかけらを入れ、その蒸気を吸い込む(※濃すぎるとむせるので注意)

気になる方は「クリスタルミント」で検索すると、さまざまな商品が見つかると思います。
薄荷とミントの違いですが、日本の薄荷の代表格である北見ハッカのようなものは、メントール含有量が多く、よりパンチのある香りが特徴です。スペアミントは比較的マイルドな香りです。
ミントは、入浴剤やアロマオイルとしても利用できます。
帰経(どの臓器に作用するか)
• 肺経:喉の痛みや風邪症状の緩和
• 肝経:イライラや目の充血を鎮める
薄荷が配合されている漢方薬
• 逍遙散(しょうようさん) ストレスによる肝気鬱結(うつ症状)を改善
• 加味逍遙散(かみしょうようさん) 精神不安を改善
注意⚠️子宮収縮作用があるので妊娠中は避ける。また幼児には刺激が強いです。
ハトムギ(薏苡仁:ヨクイニン)
雑穀米に入っていることが多いハトムギです。微寒性 涼性の食薬です。ハトムギ茶もそうです。殻を除いたものが漢方薬に使われるヨクイニンです。ハトムギは、癖がなく、米と一緒に炊くと、見た目はもち麦に似ています。体内の湿気や熱を取り除き、湿疹を改善します。むくみ解消効果にも。ハトムギ化粧水として外用の抗炎症作用があります。
夏用の食薬としてよく使われ、体が冷えやすいので、寒い時期は、生姜やシナモン、山薬(山芋)などと組み合わせると涼性が中和されます。
写真は、ハトムギ入りご飯です。軽くて浮くので米を洗った後、そのまま入れます。紫蘇梅干しと共に。


帰経
・脾経・胃経:消化機能を強化、むくみや下痢を改善
・肺経:皮膚のトラブルや痰の絡む咳に対応
注意⚠️ 利水作用があるので、乾燥肌体質は気を付ける。
艾葉(よもぎ)
温性のよもぎの生薬であるガイヨウ(艾葉)には、抗炎症 抗菌、抗酸化作用があります。蓬餅、よもぎ茶など身近によく使われています。私が大好きなスーパーハーブです。
五味のうちの辛味を持ち、気血の流れを促進し、停滞を解消し、苦味は、熱を冷まし湿気を乾かします。
入浴剤にもよもぎを乾燥した葉っぱを使います。4月初旬ではまだよもぎがそれほど成長していませんが、新芽は食材に使いやすいです。道端の雑草の中で探し出して摘み取れ乾燥させれば、次の年も香りそのままに使えます。お茶は乾燥させたものを煎じます。
帰経
・肝経:血の貯蔵と調節に関わり、生理痛や冷えを緩和
・脾経:消化機能を整え、出血を止める
・腎経:下半身冷え、腰痛、頻尿に対応
アレルギー対策その他とまとめ
以上、身近にある食薬、ハーブのアレルギーの対処法になります。
その他に生薬として地黄、百鮮皮。
薬膳では、オメガ3脂肪酸含み炎症を抑制する青魚の鯖、イワシ、
菊花茶
生姜と大根のスープ
クコの実
緑豆(おかずのスープやご飯に足したり、デザートにも)
ターメリックミルク(ウコン黒胡椒に豆乳を入れる)
腸内環境を整えることでアレルギー反応を低減する味噌や納豆の発酵食品
保湿や荒れた肌の修復に、白キクラゲ、レンコンがあります。柑橘類のジャバラジャバラも試したことがあります。
体質があるので、全く効かないものもあるかもしれませんし、ピタッとハマるものもあるかもしれません。私は、諦めず、色々トライします。
ポイントは、全方位、食事と外用的な入浴剤、アロマ、漢方薬、市販薬や処方薬、防御にマスクやメガネ、スプレー、着替え、になります。
アレルギーの不快感の低減に何か参考になれば幸いです。
また、間違った内容があれば、ご指摘頂けたら嬉しいです。